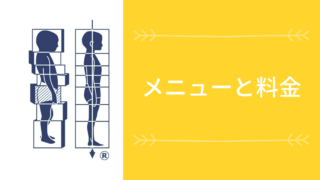認定ロルファー™の利香です。
幼い頃の愛読書のひとつが『家庭の医学』と『ブラック・ジャック』だったのに、医者になりたいと熱烈に願ったことはない。人を「治す」ことよりも、病のメカニズムの不可思議さに心を惹かれ、病によって身体的・精神的に人が変容してゆくプロセスに興味が尽きないという、ちょっとヘンな子どもだった。
細菌、ウィルス、寄生虫…ありとあらゆるものがヒトを殺しにくるし、遺伝子の異常によってもヒトは苦しめられる。その不条理が不思議でならず、体になにが起こるのかを具(つぶさ)に知りたいという欲求に衝き動かされる。
『死体が語る歴史 古病理学が明かす世界』を読むと、ヒトの歴史はすなわち病と労働との戦いであることがよくわかる。集団墓地に埋葬されたあらゆる世紀の一般人(王侯貴族以外という意味)の骨には関節炎の痕がもれなく残っており、農耕や牧畜といった日常の労働の厳しさを物語っている。家畜と密に接する仕事についていた場合は、寄生虫の被害も侮れない。仮に王侯貴族であろうとも人類は長らく結核の脅威から免れ得なかったこともよくわかり、ワクチンの偉大さを思い知る。
現代では一部の人たちから猛烈な反発をくらっているワクチン、そして免疫システムにおよぼす影響の大きさがだんだんわかってきた抗生物質だが、このふたつがなかったら、新生児の大半は死に、仮に生き延びてもあらゆる病や怪我が致命傷となり、人類の平均寿命はおそらくよくて40代どまりであっただろう。これはなんら驚くことではなく、およそ100年前、1920年(大正9年)の日本の平均寿命は男性42歳、女性43歳である。もちろんだからといって60歳以上の人が滅多にいなかったわけではなく、これは乳幼児の死亡率の高さに起因する。子どもが無事に育ちあがらないのが当たり前の世界だったわけで、それを考えたらワクチン反対など容易に言えたものではない。

今日のわたしたちが多大な恩恵に浴している解剖学(アナトミー)は、中世以降の欧州の大学あるいは王室付きの外科医たちの”熱意”によって成り立っている。とはいえ、今日のように冷凍/冷蔵設備や技術もない時代に、解剖するための新鮮な死体を手に入れるのは非常に困難だった。18世紀ともなると「夜になると、遺体をめぐって墓地で殴り合いが起き、怪我をしたり殺されたりする者も出た」り、処刑された罪人の遺体をキリスト教式に埋葬したいとする家族や支援者たちと、「死体を手に入れようとする医者や外科医たちとの間で衝突が起きることもたびたびあった。とりわけイギリスのタイバーンでは、ある公開処刑でまさしく暴動が発生し、絞首台より群衆の中に大勢の死者が出た」りしたというのだから、なんとも言い難い気持ちになる。
X線の発明直後、初めてレントゲン写真で自分の頭蓋骨をみた医師が、ショックのあまり不眠症になって戸棚の奥深くにその写真を隠してしまった話など、今日から考えたら「おいおい!科学者だろう!?」と叫びたくなるようなエピソードも散りばめられていて、笑ったり驚いたりしたあとには「待てよ…。こんなにドライなわたしの方がおかしいのか…?」とふと真顔になる。
本書は死体恐怖(ネクロフォビア。埋葬した死体が墓からでてきて悪さをするという恐怖)や吸血鬼信仰、古代の都市と衛生、中世以前の奇形の人々の処遇といったものにも触れているが、いずれも章としては短く簡潔かつ難解な専門用語があまりないので読みやすい。論文または小論の集積というよりも、手軽な読みものといった感じにまとめられているのは、翻訳者の功績に負うものかもしれない。
わたしたちが当たり前とみなしている死生観や病に対する価値観、それの根幹となっている信仰や倫理が、実は非常に流動的かつ相対的なものだということをも教えてくれるので、進路に悩むちょっとヘンな中高生にも読んでもらいたい。
フィリップ・シャルリエ著、吉田春美訳『死体が語る歴史ー古病理学が明かす世界』(河出書房新社,2008)
↑上記リンクをクリックするとAmazonに飛びます