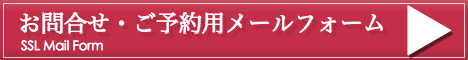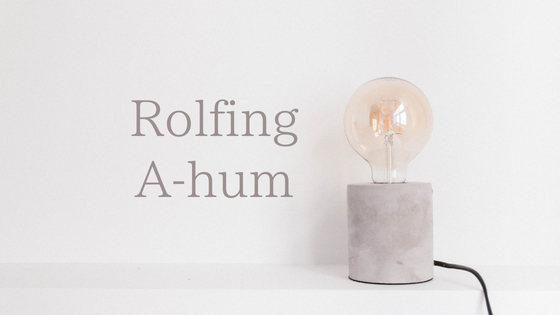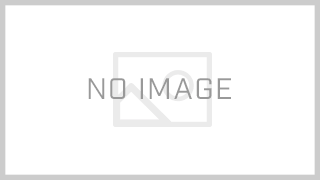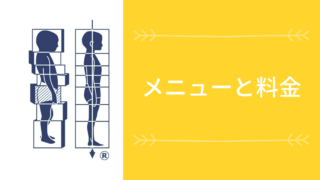「ほんとに寝てるヒマないのねー(笑)」と
先日、セッション中に
クライアントさんに言われました。
そうなんです。
ロルフィングのセッション中、
クライアントさんには、
「脚をこういう風に動かして」とか
「首の後ろの力を抜いて」とか
「お尻に尻尾があると想像してみて」とか、
ロルファーが出す指示(キュー)に従って
あれこれやっていただくことになります。
だからクライアントさんはけっこう忙しい。
実際に手足を動かすことから、
ただ思い描いてみることまで含めて、
その時々のセッション内容によって
何をどの程度していただくかは様々です。
ロルファーとクライアントの組み合わせによって
キューのバリエーションは無限に増えます。
一言で言うなら、ロルフィングの施術は”クライアント参加型”です。
マッサージならリラクゼーションも効果の一つなので、施術をうけながら寝てしまっても起こされることはありません。
柔整体や理学療法の現場でうける、制限をとってリハビリ効果をあげるためのマッサージでも、患者は受け身でされるがまま状態でほぐしてもらいます。私の大好きな鍼灸も、基本的には施術中はじっと静かにしていることが普通かと思います。
ところがロルフィングの場合はじっと黙ってなされるがままではいられません。あれしろこれしろと声をかけられるので(それでも寝落ちすることは多々あります。半分起きて半分夢うつつという状態にもわりとよくなります)クライアントも忙しい。
なんでこういうスタイルなのかというと、ロルフィングでは、最終的に、クライアントさんに自分の体の主導権をしっかり自覚的に持ってもらうことが目的で、そのため身体に対する感覚を呼び覚ますことが必要になるからです。
私たちは普段は体の感覚を、だいぶおろそかにしています。ちゃんと動いて当たり前とみなしていて、痛みや痺れがでて初めてその部位の存在を意識します。そして今度は不具合があるところばかり気になってしまい、他のところはそのまま放置しがちです。過度に敏感になっているところの感覚は適度に、意識がゆきわたっていないところにはまずは感覚を呼び起こす。そういう作業をロルフィングのセッションの中では繰り返してゆきます。
体の感覚を感じ取るアンテナを、できるだけ均等に持っていれば、ゆがみや不具合がひどくなる前に「あ。なんか変だな」と自分で気がついて早めに調整できるようになります。そういうアンテナを持つのも、小さな変化に気がつくのも、それを言葉にして認識したり伝えたりするのも、クライアントさん自身にしかできません。
何事も練習が大事。自分の体のどこが今どんな風な感じがしているのかを言葉にして他人に伝えようとすると、最初はちょっと難しく感じられるかもしれません。セッション中やセッション後に、今、どんな感じがしているか、体をどのように感じ取っているかを何回も質問され、「そうだなぁ…どんなかなぁ…なんて表現したらいいかなぁ」と考えをめぐらせつつ、体の中を一生懸命探りつつ、他人にも伝わる言葉に変換してゆく。
言葉にする=名前を与えることで、よりその感覚ははっきりと知覚されるようになります。
何をどのように表現してもいいんです。
詩人になってもいいし、自分の得意分野でのたとえ話でもいいですし、もちろん、身振り手振りをつけつつ表現していただくのも大歓迎です。
その練習も是非楽しんで受けていただきたいなと願っています。
ちなみに、私が今まで受け取ったフィードバックで、とても素敵だなぁと思ったのは「腰から下が綿あめのよう」というものでした!
ふわふわで甘やかで幸せな感じまでが伝わってきて嬉しかったです。
いろんな人にこういう感覚をお届けしたいものです😊
**メルマガ登録**
もっと詳しくロルフィングを知りたい方むけに
ロルフィングの基本になる「10シリーズ」を
ゆるく解説するメルマガを配信しています。
無料配信登録は下記URLからどうぞ!
https://mail.os7.biz/add/nN9K
*そもそもロルフィングってなんだ?な方はこちらをクリック。
*お問合せ、ご予約はこちらのバナーをクリックしてください。