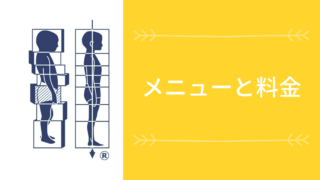十川信介先生が亡くなった。一昨年、八十歳のお祝いをしたところだった。大学院の7年間ずっとお世話になった恩師の訃報に接して動揺。悲しい。ただただ悲しい。

就職後も先生の指導と庇護のもとにいたようなものだったので、先生はわたしの「後見人」みたいな存在だった。喧嘩っ早くて傲慢で無知でどうにもならなかったわたしを拾って、研究者のヒヨコにまで育ててくれた恩師だった。誰の前にでても緊張することがほとんどないわたしだが、先生の前では常に畏れを感じていた。知識量と見識の深さが量でも質でも圧倒的に自分より勝っている人の前に出ると、人は畏怖の念しか感じないものだということを初めて知ったのも、先生のゼミでだった。博士号をとることが恩に報いることだと思っていた。
わたしはまたアカデミックな世界に戻って博士論文を書くのかもしれない。そういう選択肢も人生にはあるのかもしれない。でも今は、現在やっているボディワークのことも文学研究も、両方バランスよく出来るほど器用ではないことを自覚している。
わたしの選択を「まぁ、しっかりやりなさい。君が決めたことなんだから、しっかりやらないとダメですよ💢」と叱りつつもいつも認めてくれた先生には、感謝しかない。
大学院にゆくということはどういうことなのか、院生の視点から考えることはあっても、わたしは最近まで育てる側の視点から考えたことがなかった。大学生から修士コースへと入学してくる志望者を選び指導するというのは、未来の高等教育を担う人材を選別して育成することであり、自分の後継者を育てることなんだ。研究者の一生なんて短いものだから、自分の亡き後にこの分野の研究を引き継いで充実させ、実り多いものとしてくれる後継者を少数精鋭で育てること。それが大学院生を教育するということ。
浅はかなわたしはそのことに無自覚に生きていた。わたしがどれほど期待され、愛されていたかを知らなかった。「あいつはいろんなことをよく知っていてなかなか優秀なんです」と職場の先輩にこっそり言ってくれていたことを後で知り、ただ涙。
厳しく育ててもらったおかげで、論文の質の見極め方、一次資料の探し方、資料の取り扱い方、引用の仕方、論理的に考える思考、言葉を峻別する感性とマナーを身に付けることができた。そのことに感謝し、先生のご冥福を祈る…しか、遺された者にできることはない。せめてあと一目、お会いしたかった。